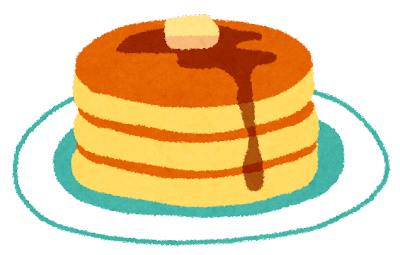
普段何気なく使っている「おやつ」
でもふと考えたときに、何で「おやつ」っていうんだろう??と疑問に思ったので調べてみました
「おやつ」の由来は?
昔はよくおやつの時間は午後3時でした
あの有名なカステラのCM
カステラ一番、電話は二番、三時のおやつは文明堂~
というのもありましたね
ちなみに、この電話は2番って何の意味でしょう?
この文明堂のキャッチフレーズが誕生したのが昭和10年(1935年)のこと
この時に、各地域の電話局の電話番号「2番」を買いそろえていたそうです。
当時は電話交換手が電話を取り次いでいた時代で、電話口で「2番」といえば文明堂に連絡できるようにしていたというワケです
話がそれましたが
今ではお菓子とかケーキなんか食べるのも時間も関係なく「おやつ」といってますね
遠足なんかでも「おやつ」はいくらまで!とかありますね
バナナはおやつなのか?というのも昔良く言ってました(年がばれますねww)
前置きが長くなってしまいましたが
ではこの「おやつ」の由来はどこから来たのでしょう?
江戸時代の中期ごろ、今の午後2時から4時にあたる時間を「八刻(やつどき)」と言っていました。
ちなみに
江戸時代は1日を12刻としていました
この事から終日のことを「二六時中(2×6=12)」と言っていました
現在は24時間であるため「四六時中」といっています。
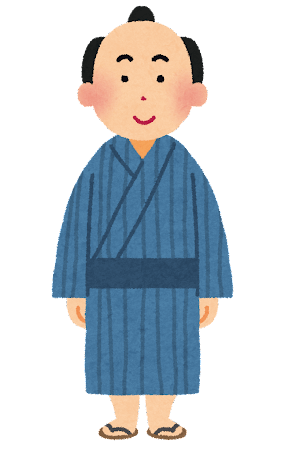
江戸時代中期ごろまでは、食事は基本的に1日2食
当然お昼過ぎにはお腹がすきますね
だいたいこの八刻(14時~16時)に間食をとることで体力を持続させていました
やつどきに食べる軽食から「おやつ」という名前になったといわれています
そしてこのおやつは働いている大人の世界のものでした
当時は子供が食べるという考えはありませんでした
おやつが子供にまで広がったのは明治時代になってからです
最初は栄養補給のために食べるためだったそうです
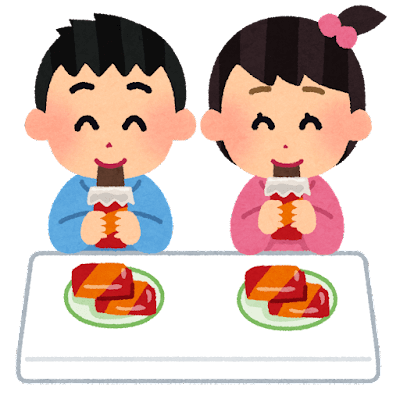
最近は間食が多く腹回りが気になってきました・・・
CHECK!